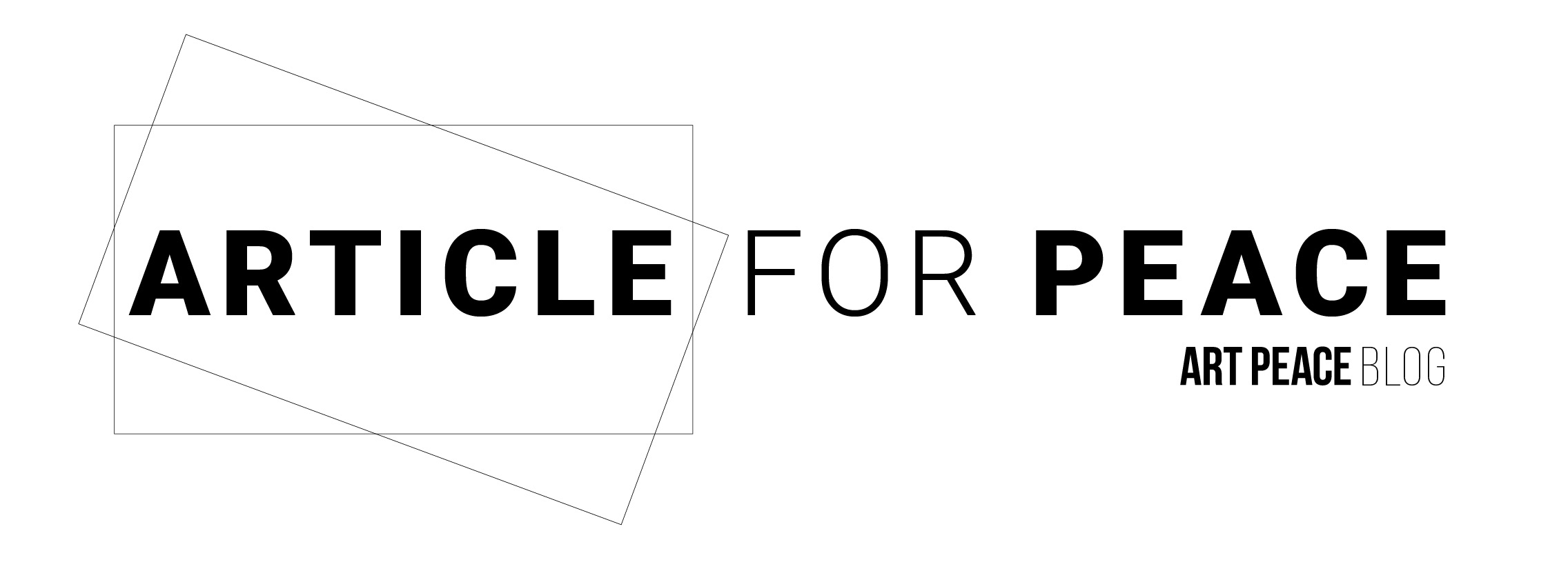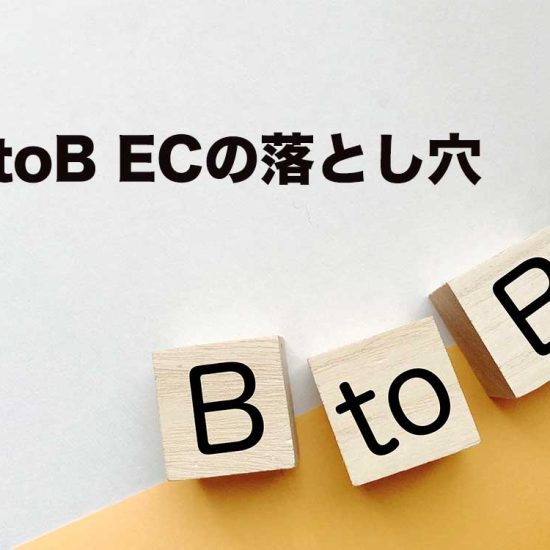目次
SEOだけでは成果につながらない時代に
「検索で上位にあるのに、なぜか成果につながらない」 「アクセス数はあるのに、問い合わせや購入が伸びない」
そんな課題を感じていませんか?
これまでのSEO(Search Engine Optimization)は、検索エンジンに評価されるコンテンツを作ることが主な目的でした。しかし、2025年のWEB制作においては、それだけでは不十分です。
これからは、検索ユーザーが求めている”体験”を最適化すること、すなわちSXO(Search Experience Optimization)が鍵になります。
検索順位を上げるだけではなく、ユーザーの意図や心理に寄り添い、最終的な成果(CV)に導くことが求められているのです。
SXOとは?SEOとの違いを解説
SXOとは、Search Experience Optimizationの略で、検索体験の最適化を意味します。
SEOが検索エンジンへの最適化を目的とするのに対し、SXOはユーザーにとっての最適な検索体験を提供することを重視します。
たとえば、ユーザーが「採用サイト 作り方」と検索したときに、
- 魅力的なタイトルとメタディスクリプションでクリックを促す
- ファーストビューで「採用サイトに必要な要素」がすぐ分かる
- 読みやすく、構造化された記事で情報を深掘りできる
- 最後に「制作相談はこちら」と導線が明確にある
こうした一連の体験が設計されている状態こそが、SXOです。
検索意図を汲み取り、ページの設計・構成・デザインすべてに反映することで、ユーザー満足度と成果が大きく変わります。
なぜ今、SXOが重要なのか?
① 検索ユーザーの“離脱スピード”が上がっている
スマホでの検索が主流となり、ユーザーは数秒で「読む/離脱する」を判断しています。
ページの表示速度、見やすさ、直感的な構造が求められ、コンテンツの質だけでは成果につながらなくなっています。
② E-E-A-Tの強化と“信頼できる体験”が重視される
Googleが重視するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)との相性もSXOは良好です。
- 会社や筆者の顔が見える
- 実績や事例がある
- 誰のために書かれた情報かが明確
これらはすべて、“体験としての信頼”につながります。
③ ユーザーの期待が“コンテンツだけ”では満たせない
検索ユーザーは単に情報を読むだけではなく、課題を解決したいと考えています。
たとえば:
- 「料金の目安がすぐ知りたい」
- 「制作会社の雰囲気がわかる実績が見たい」
- 「自分に必要なサービスかどうかを判断したい」
こうした行動意図を先回りしてサポートする導線や情報設計がSXOです。
SXO視点でのWEB制作・リニューアル設計のコツ
SXOを意識したサイト制作には、次のようなポイントがあります:
- 検索キーワード×ペルソナでページ設計
- 「キーワード」ではなく「検索意図」を軸にページ構成を考える
- ファーストビューで目的が伝わる設計
- たとえば診断ボタン、導入事例のリンク、要点のまとめ など
- UXライティング+マイクロコピー
- ユーザーの不安を先回りしてフォローする表現を配置
- CTAや相談導線が“自然”に組み込まれている
- 押しつけ感なく「もっと詳しく知りたい」をサポート
- SEO担当とデザイナーが“共創”する制作体制
- 記事とUI/デザインを分けずに一体で考える
まとめ:検索“される”から、“体験される”WEBサイトへ
SXOは、単なる新しい流行語ではありません。 「ユーザーが求めている体験を、検索結果から始めて、サイト内で完結させる」 という、極めて本質的な考え方です。
検索エンジンの評価だけでなく、ユーザーの“納得感”を設計できてこそ、成果につながるサイトが作れます。
2025年は、SEOからSXOへ──“見つかる”から“選ばれる”サイトづくりへ。
ぜひARTPEACEにお問い合わせください